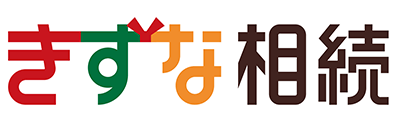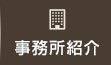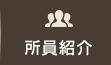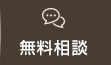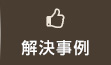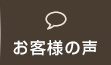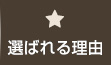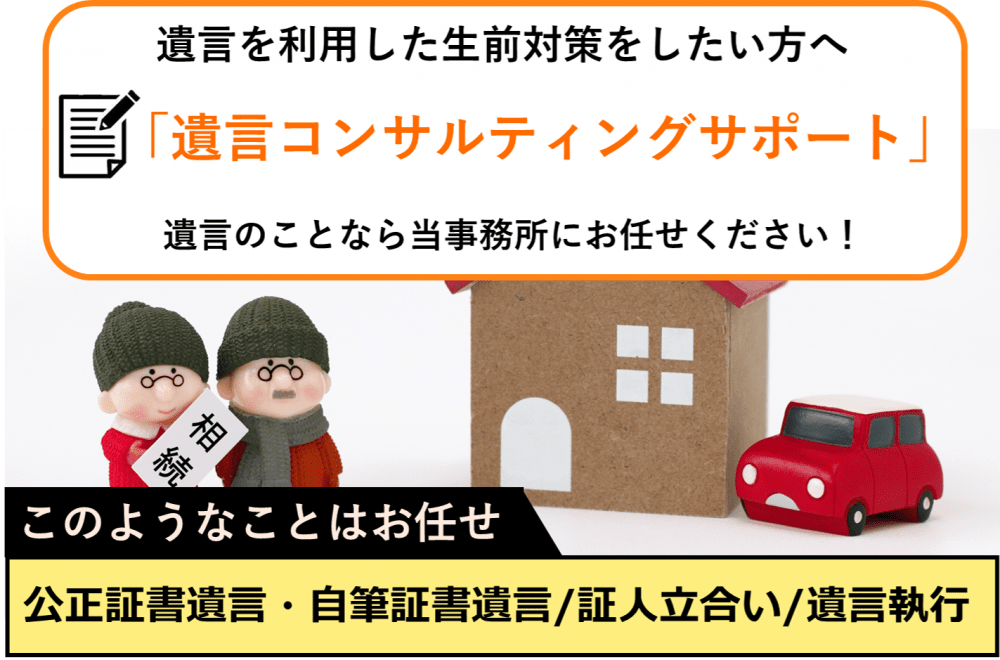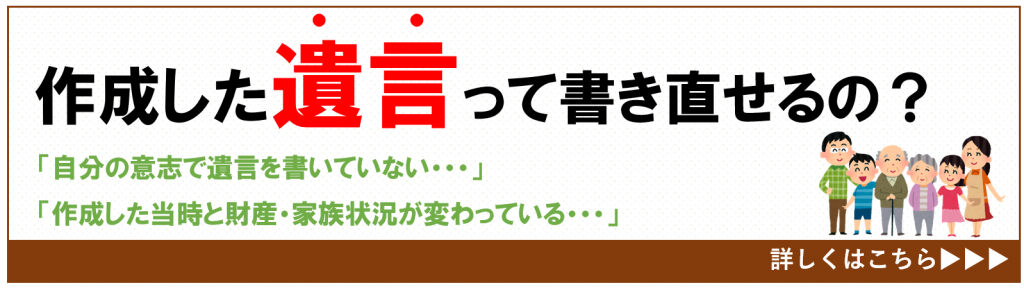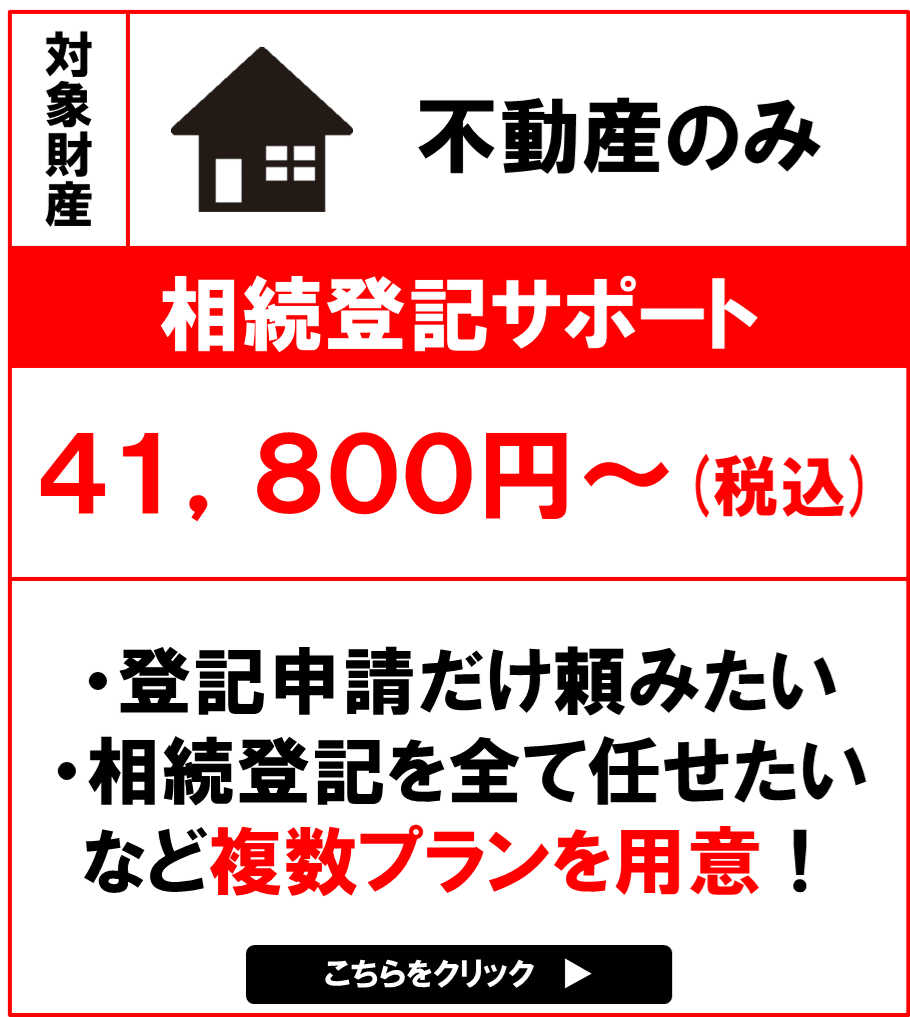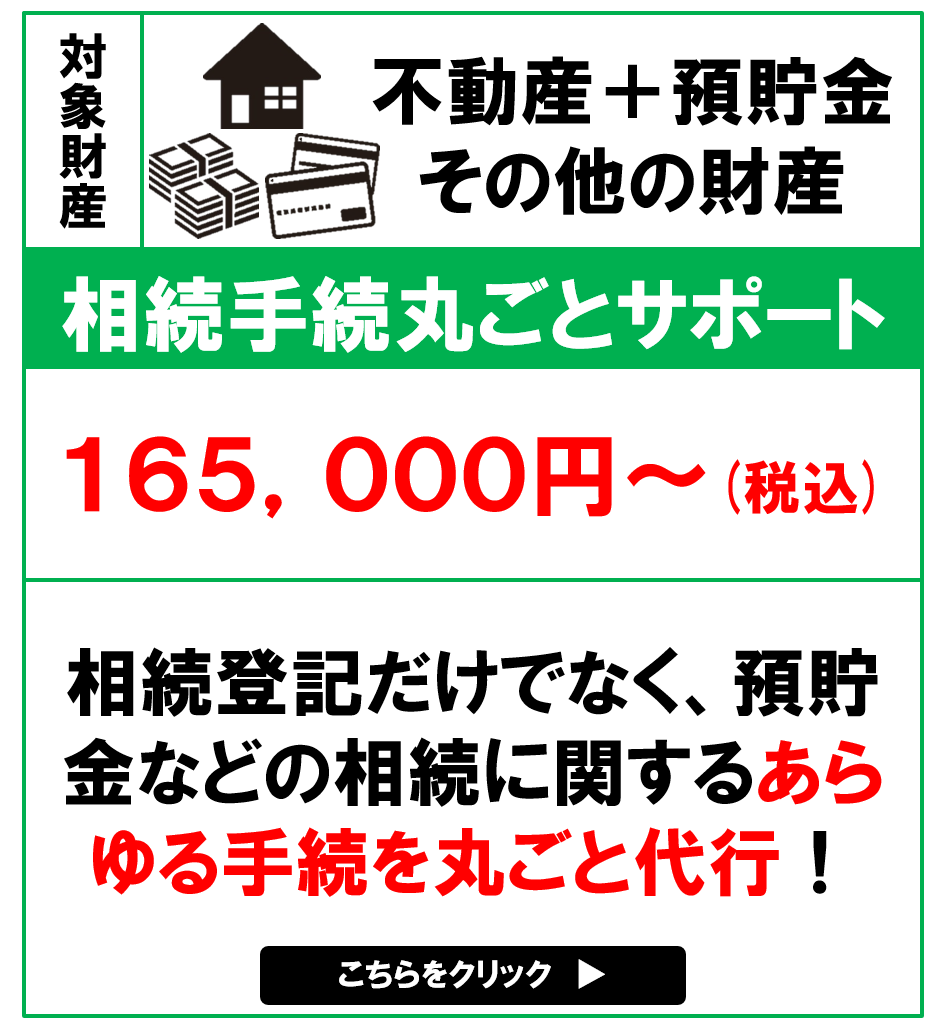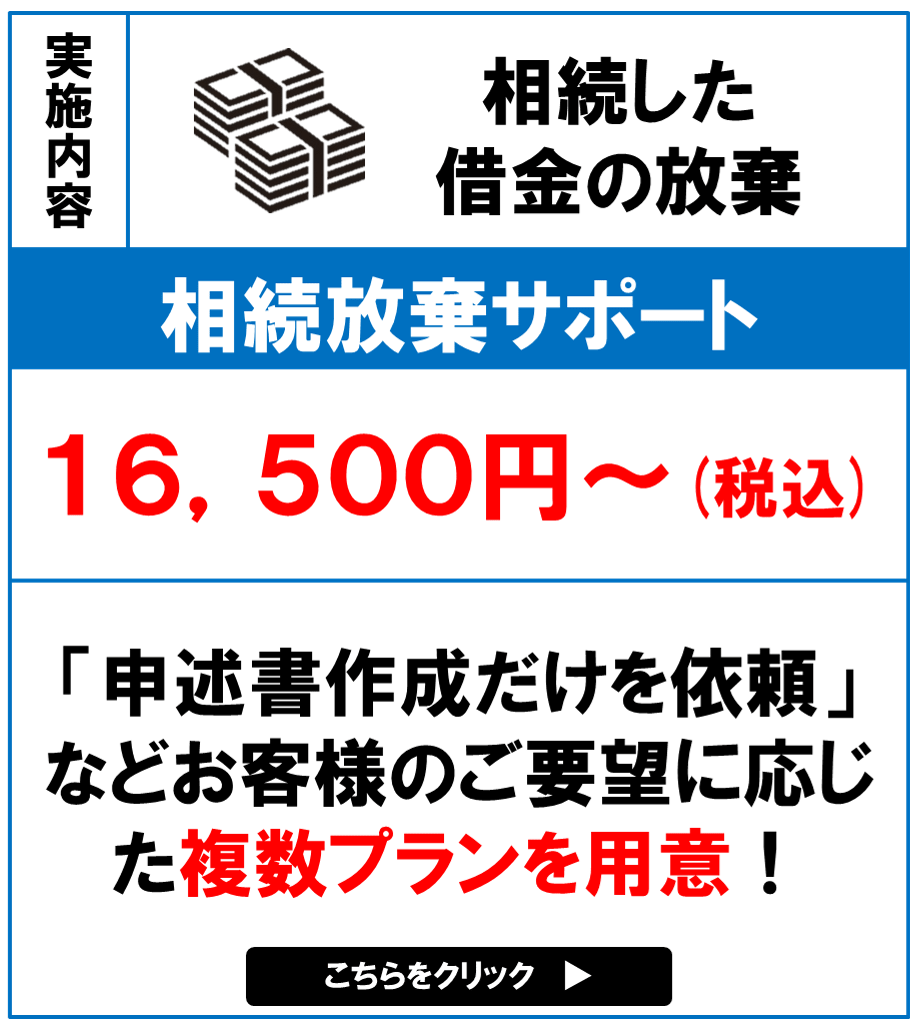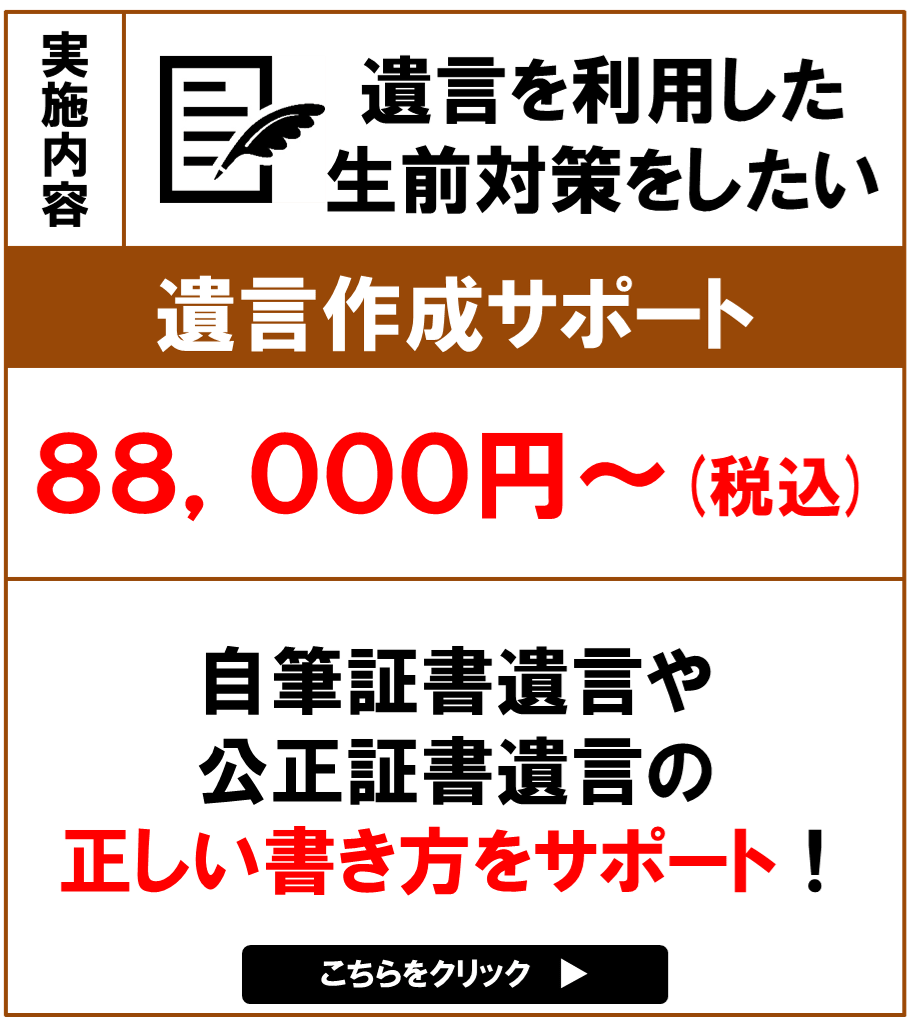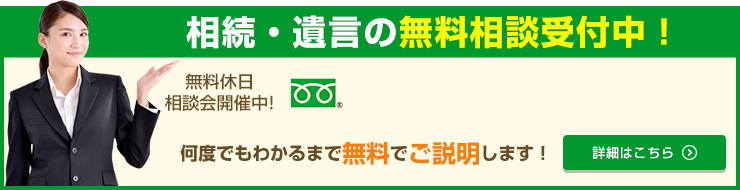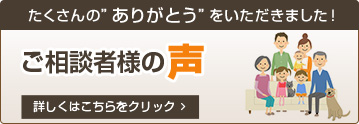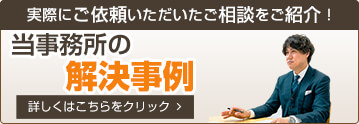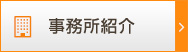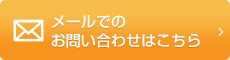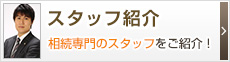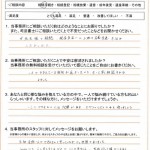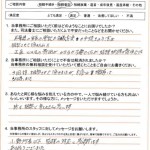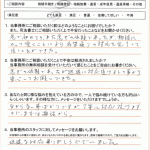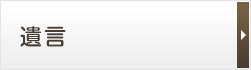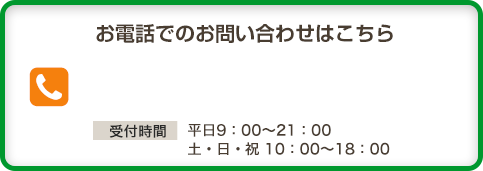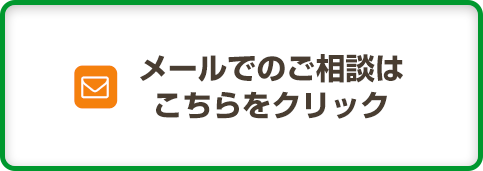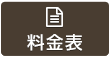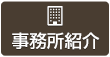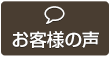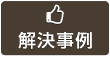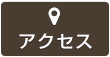【司法書士が解説!】遺言書が増えても、争続は減らない理由 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

-
遺言書を書けば相続争いは防げる?現場が見た争族のリアル
「遺言書を書けば、相続争いは防げる」──そんなフレーズを耳にすることが増えました。
自筆証書遺言保管制度の導入やメディアでの啓発もあり、遺言を書く人は確実に増えています。ところが、司法書士として現場に立つと、遺言があるのに争っているケースが決して少なくありません。
たとえば、長男に全財産を相続させると書かれた遺言を残した父親。しかし、次男・三男は「なぜ自分たちにはないのか」と不信感を募らせ、家庭裁判所に持ち込まれるほどの対立になった──そんな事例も珍しくないのです。
遺言書は“誰に何を渡すか”を決める強力なツールですが、書いただけでは家族の気持ちまでは整理できない。この「法と感情のズレ」こそ、今の日本の“争族”問題の核心かもしれません。
2. 遺言書が増えた背景
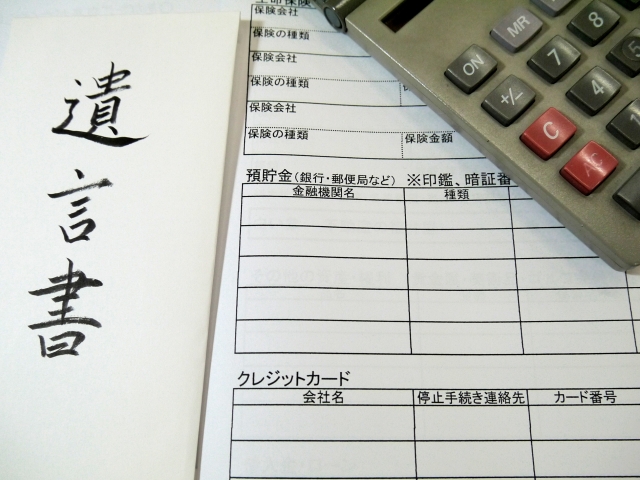
近年、遺言書の作成件数は確実に増えています。背景にはいくつかの要因があります。
まず大きいのは、法改正と制度整備です。2019年に「自筆証書遺言保管制度」がスタートし、自筆の遺言を法務局で安全に預けられるようになりました。従来、自筆の遺言は自宅保管が多く、紛失や改ざん、死後の発見遅れが課題でしたが、この制度により心理的ハードルが下がりました。また、公正証書遺言も件数が右肩上がりで、2023年には過去最高を更新しています。
さらに、高齢化の進展と家族のかたちの変化も影響しています。死亡者数の増加に伴い相続件数自体が増え、再婚家庭、子どものいない夫婦、事実婚など多様な家族が一般化。相続にまつわる利害関係が複雑化し、「揉める前に備えたい」という意識が強まっています。
そしてもう一つは、士業やメディアによる啓発活動です。司法書士や弁護士によるセミナー、新聞・テレビの特集が「遺言=トラブル防止」というイメージを社会に浸透させました。
こうした制度・社会・情報の三重の変化が重なり、今や遺言は特別な人のためのものから「誰もが考えるべき備え」へと広がりを見せています。
3. それでも争いが起きる3つの理由

(1) 内容が唐突・説明不足
遺言書をめぐる相続争いで最も多いのが、「内容が唐突すぎて家族が納得できない」というケースです。
例えば「長男に全財産を相続させる」とだけ書かれた遺言。法的には明快であり、登記や銀行手続きもスムーズに進むかもしれません。しかし、次男・三男から見れば「なぜ長男だけなのか?」という強い疑念が残ります。特に、理由の記載がない遺言は、受け取る側が勝手に“裏の理由”を想像してしまうことが多いのです。
「自分は親の面倒を見てきた」「自分はあまり交流できなかった」など、家族の立場や感情はそれぞれ異なります。理由が書かれていないと、「親が不公平だった」と感じるきっかけになり、結果的に家庭裁判所での遺留分侵害額請求へと発展することも少なくありません。
また、唐突さの背景には、「事前説明をしないまま遺言を残す文化」もあります。「死後に知ることになる方がいい」と考える親も少なくありませんが、現場ではこれが火種になることが多いのです。
(2) 遺言の効力と感情の納得は別物
もう一つの大きな理由は、「遺言の法的効力と家族の感情的な納得はイコールではない」という点です。
遺言書は法的拘束力を持ち、基本的にはその内容が優先されます。しかし、「法的に正しい」ことが必ずしも「感情的に受け入れられる」ことを意味しません。
例えば、親が「生前に世話になった長男に感謝を込めて」と、遺産の大半を長男に残す遺言を作ったとします。法的には問題ありませんが、ほかの兄弟から見れば「自分たちは軽視された」と感じるかもしれません。
この「正当性と納得感のギャップ」が、感情的な争いを引き起こします。
さらに、相続はお金だけの問題ではなく、「愛情の証明」として受け止められがちです。相続分が少ない、またはゼロとされた子が「親からの愛情を否定された」と感じることもあり、それが感情的な対立を深めてしまいます。
士業が現場で感じるのは、「遺言書は結論を示すものであっても、納得を作るものではない」という事実です。
(3) 書くだけで終わり、伝えるプロセスが欠落
そして3つ目の理由は、「遺言を書いたら安心」と思い込み、書いただけで終わってしまうケースです。
本来であれば、遺言の内容や意図を家族に「生前にしっかりと伝えるプロセス」が不可欠です。しかし現実には、「死後に初めて遺言を目にする」という家族が多いのです。
このとき家族がどう感じるか――。たとえば、あるお母様が「面倒を見てくれた長女に全財産を」と遺言を残したケースがあります。死後、その遺言を初めて見た次女は、「母は最後まで自分を信頼してくれなかったのだ」と感じ、姉妹関係は決定的に悪化しました。
つまり、内容そのものよりも「知らされなかった」ことへのショックが争いの原因になるのです。
また、伝えるプロセスが欠けることで、「自分の判断か、それとも誰かに書かされたのか?」と「遺言の真意を疑われる」リスクも高まります。
4. 遺言書は「道具」であり、「解決策」ではない
遺言書は相続において非常に強力な「道具」です。
誰に何を相続させるか、どう分けるかを生前に指定できる法的効力を持ち、相続手続きをスムーズに進めるための羅針盤になります。しかし、現場で相談を受けていると、遺言書を「書けばすべてが解決する」「これで相続トラブルは起きない」と、まるで万能の解決策のように考えてしまう人が少なくありません。
実際には、遺言書はあくまで「意思を記録する道具」であり、それ自体が家族の感情や関係性を整理してくれるわけではありません。内容が一方的であれば、法的には正しくても「なぜ自分はこう扱われたのか」という疑念を生みます。また、本人がその意図を生前に伝えていなければ、残された家族は文字だけのメッセージを受け取り、誤解や不信が広がることもあります。
つまり遺言書は、「争いを減らす可能性を広げるための道具」ではあっても、「争いを自動的に消してくれる解決策」ではないのです。遺言書の価値を本当に引き出すためには、書いた後の対話や、内容を理解してもらう工夫、場合によっては家族信託や公正証書遺言など他の手段との併用が欠かせません。
専門家の立場から見れば、遺言書作成はゴールではなくスタートです。「書いて終わり」ではなく、「どう伝えるか」「どう納得してもらうか」まで設計することこそが、本当の意味で争族を防ぐ鍵になるのです。
5. 司法書士ができる役割

遺言書は、書いただけでは家族の納得や相続の安心までは届けられません。ここで重要になるのが、司法書士・行政書士といった専門家の関与です。私たちが果たせる役割は、単なる書類作成者にとどまりません。
まず大きいのは「調整役」としての役割です。遺言の内容や意図を、家族にどう伝えるかを一緒に考え、時には家族会議の場を設定して生前に説明を行うこともあります。理由の書かれた遺言、補足文書、メッセージを添えるなど、遺言を単なる「紙の指示」に終わらせず、「伝わる遺言」に変えていく支援ができます。
次に「遺言+α」の提案ができる点です。例えば、遺言だけでは解決しにくいケースでは、家族信託との併用や任意後見の組み合わせ、公正証書遺言の選択など、より安全で誤解の少ない仕組みを設計することができます。これにより、書類上の整備だけでなく、家族の未来まで見据えた総合的な解決を提供できるのです。
さらに、遺言執行者としての関与も大切です。専門家が執行者となれば、相続手続きの実務を円滑に進められるだけでなく、家族間の誤解や不信を最小限に抑えることができます。
司法書士・行政書士は「誰に何を残すか」を書くだけでなく、「どうすれば家族に伝わり、納得されるか」を設計できる存在です。遺言を道具として終わらせず、家族の安心につなげるための伴走者として、その力を発揮することが求められています。
6. 結論
遺言書は、相続をめぐる混乱を防ぐために欠かせない大切な手段です。しかし、「書けばそれで安心」「これで争いは起きない」と考えてしまうのは危険です。内容が唐突だったり、理由が説明されていなかったりすると、かえって家族の間に疑念や不信感を残すことになります。
大切なのは、遺言書を「書くこと」で終わらせないことです。書いた後に、どのように家族に伝えるのか、どうすれば納得してもらえるのかまでを考えることが、本当の意味で争族を防ぐための鍵となります。
司法書士・行政書士は、遺言の作成だけでなく、その意図を正しく伝え、理解してもらうための工夫やサポートを行うことができます。
「書くだけ」では届かない安心を、「伝わる遺言」に変えていくために。私たちは、これからも専門家として、そして家族に寄り添う伴走者として、その役割を果たしていきたいと考えています。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。