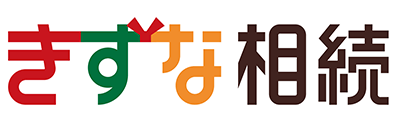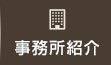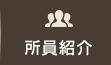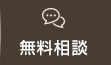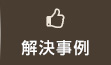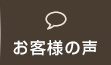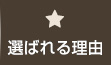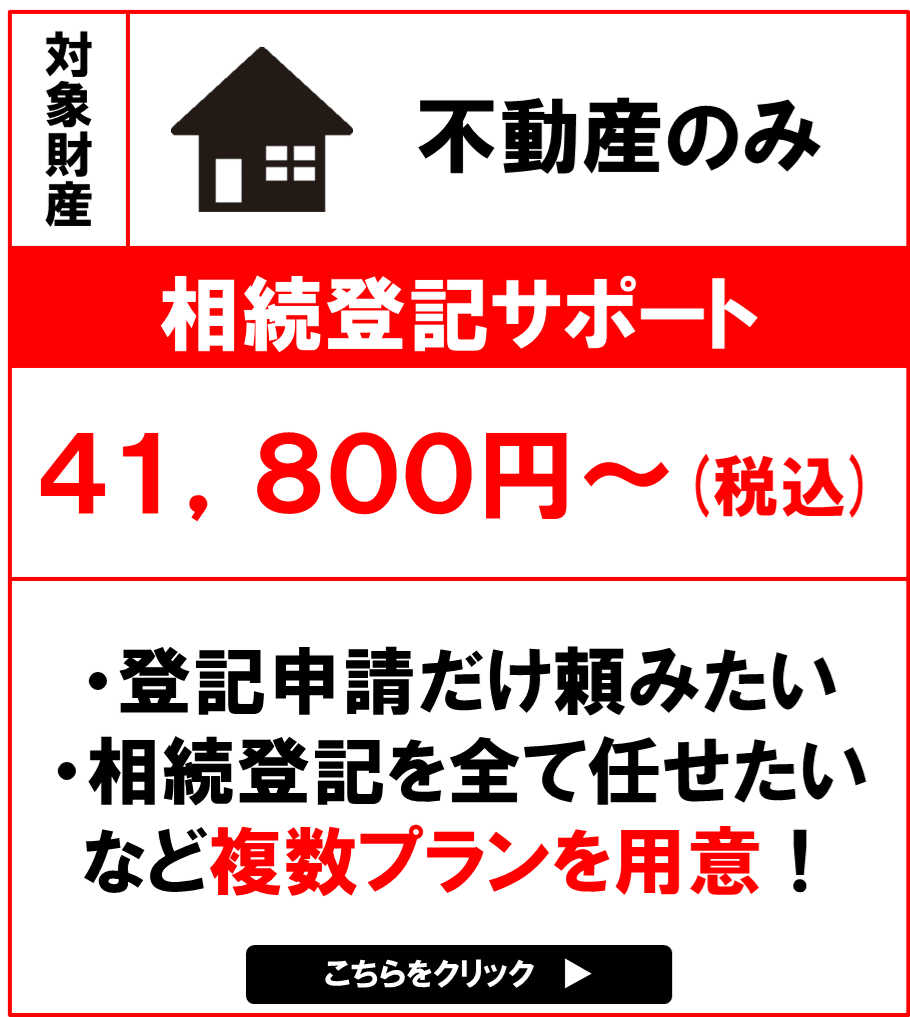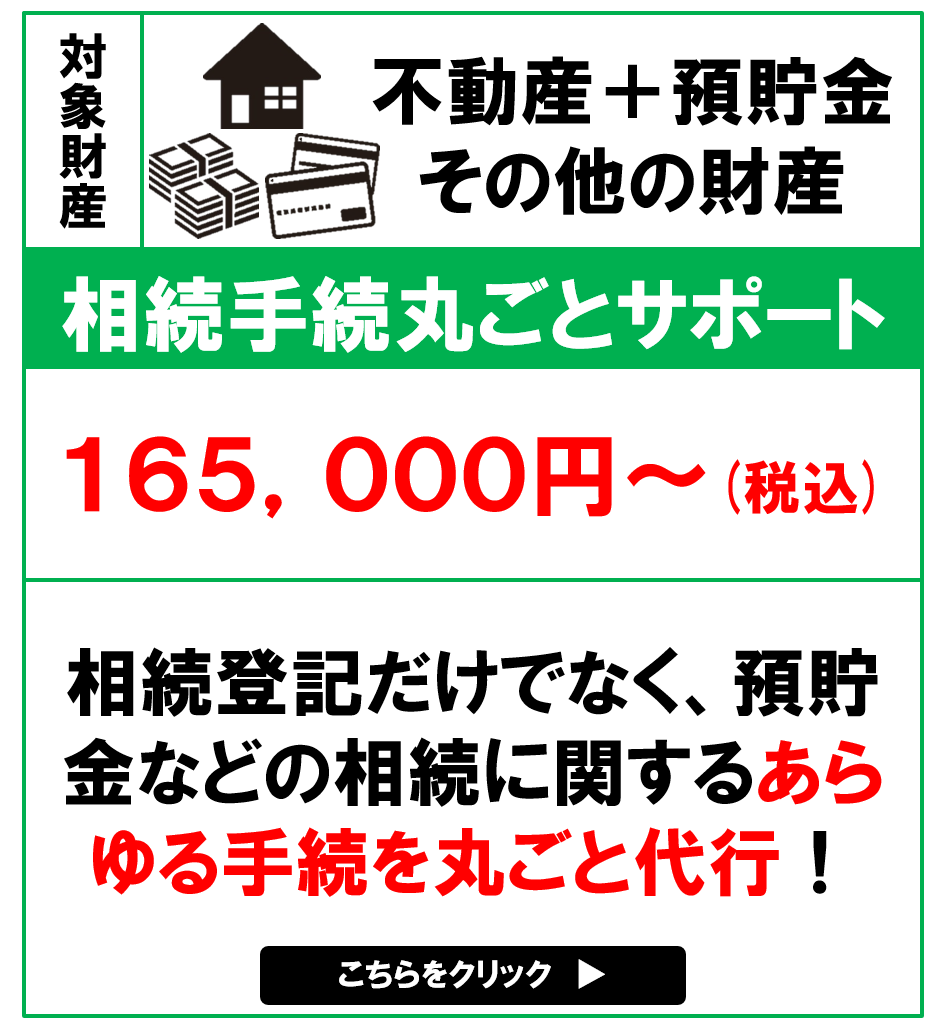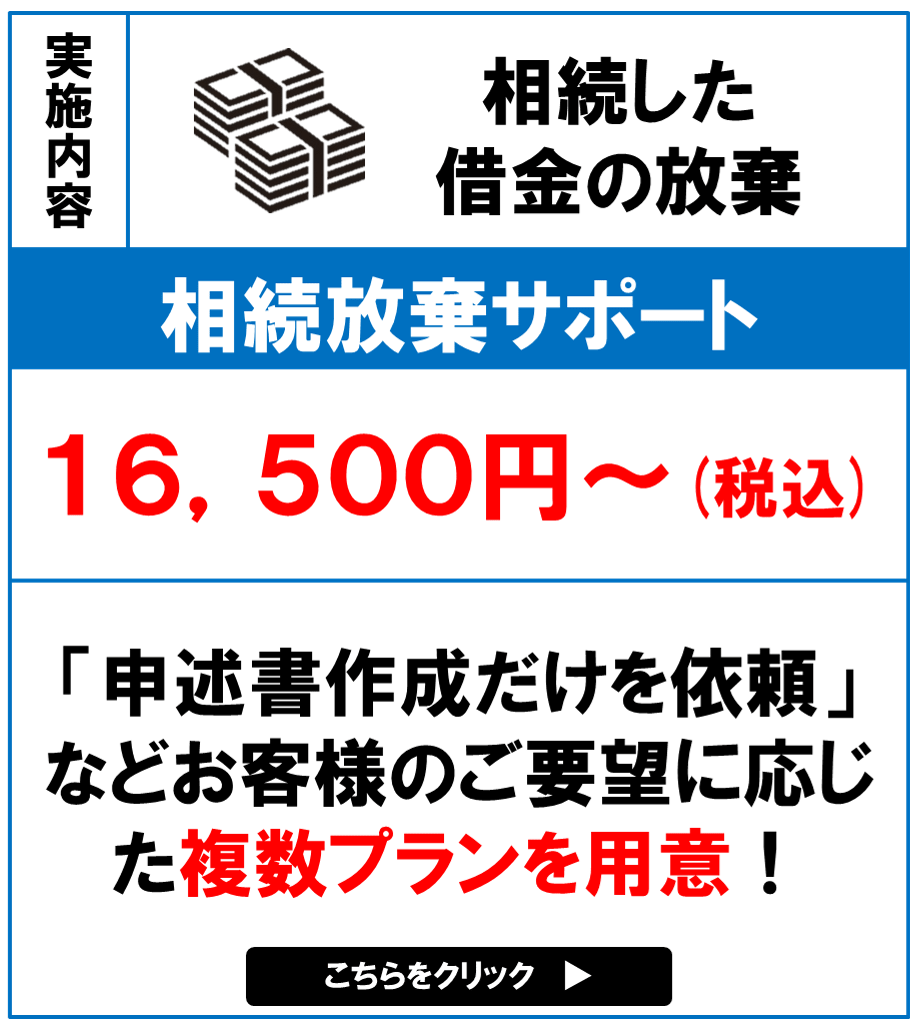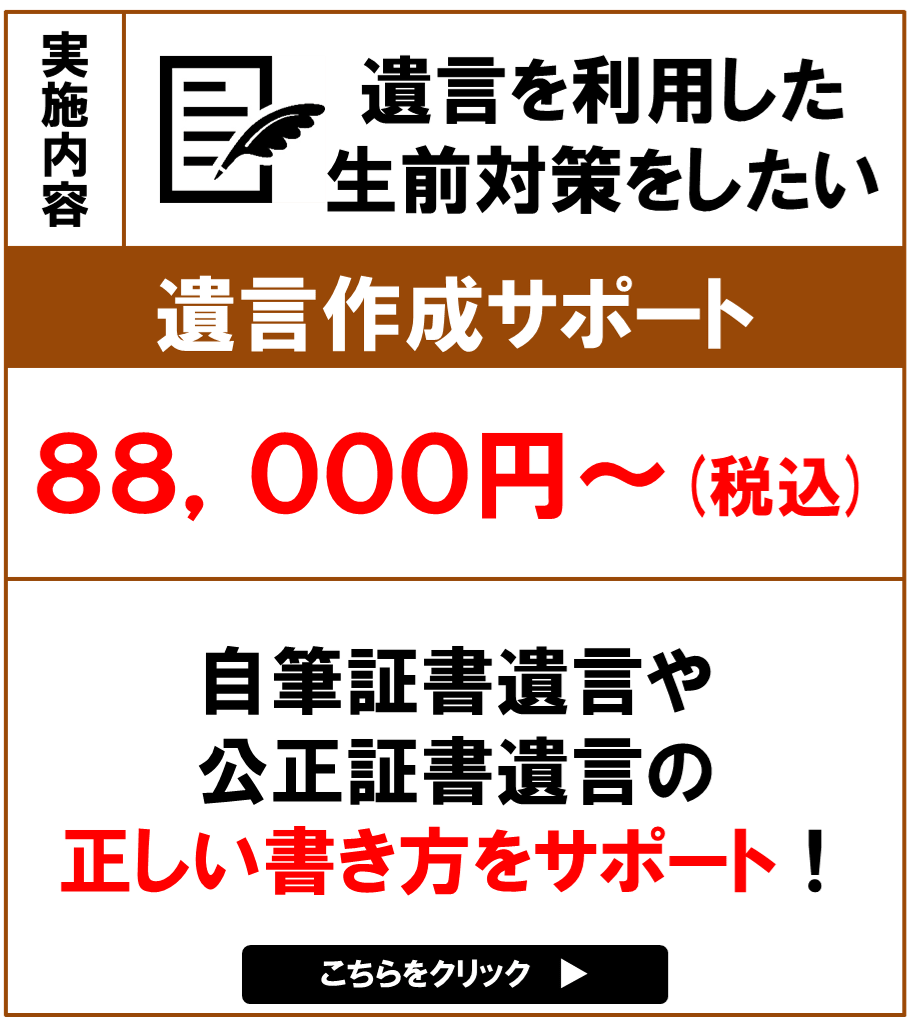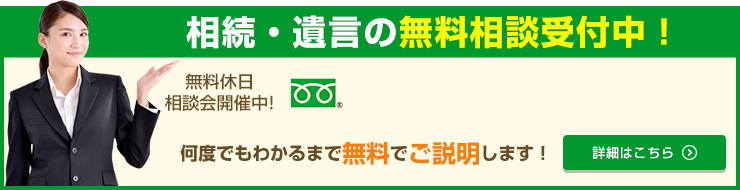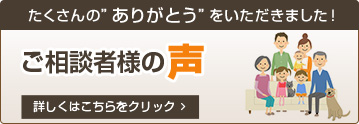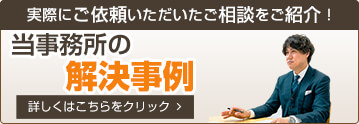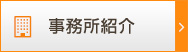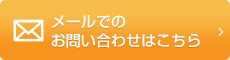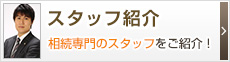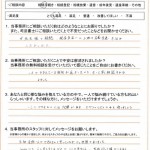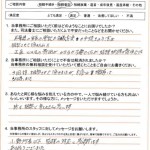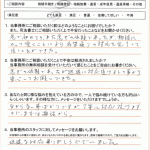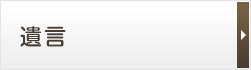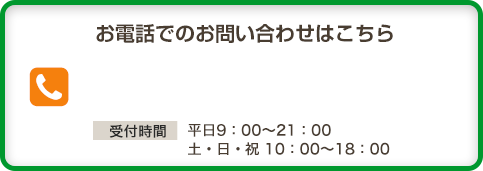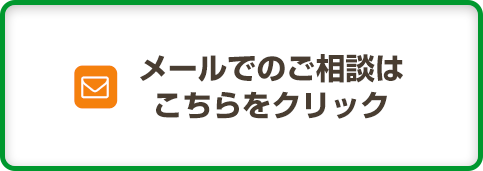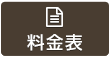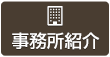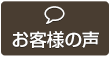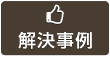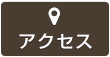【司法書士が解説!】再婚相手の連れ子に相続権は?養子縁組の有無とトラブル防止策 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

「今の妻(夫)には連れ子がいる。家族みんな仲が良く、本当の子どものように思っているが、もし自分に万が一のことがあった時、この子に財産を遺せるのだろうか?」
近年、再婚は決して珍しいことではなくなりました。
それに伴い、このようなご自身の相続に関するご相談が私たちの事務所にも多く寄せられています。
大切な家族だからこそ、お金のことで揉めてほしくない。それは誰もが願うことです。
この記事では、相続の専門家である司法書士が、再婚相手の連れ子と相続の問題について、法律上のルールから具体的な対策、そして思わぬトラブルを未然に防ぐための知識まで、分かりやすく解説します。
【結論】原則、再婚相手の連れ子に「相続権はない」
まず、最も重要な結論からお伝えします。
あなたが再婚相手の連れ子と養子縁組をしていない場合、法律上の親子関係がないため、その子にあなたの財産を相続する権利は発生しません。
たとえ長年一緒に暮らし、「お父さん」「お母さん」と呼び合う関係であっても、実の親子同然の生活実態があったとしても、法律上のルールは別です。
相続権は、法律で定められた「法定相続人」にのみ認められます。
そして、法定相続人になるのは、血のつながりのある「血族」か、法律上の親子関係を結んだ「養子」だけなのです。
再婚家庭における相続関係
・あなたと配偶者:婚姻関係にあるため、配偶者は常に法定相続人です。
・あなたと実子:血族であるため、実子は法定相続人です。
・あなたと連れ子:血のつながりはなく、養子縁組をしていない限り、法律上の親子関係はありません。→ 法定相続人ではない
では、大切な連れ子に財産を遺すにはどうすればよいのでしょうか。具体的な2つの方法を見ていきましょう。
方法1:【養子縁組】をして法律上の親子になる
連れ子に財産を相続させるための最も確実で一般的な方法は、「養子縁組」です。
養子縁組をすると、連れ子は法律上、あなたの「実子」とまったく同じ立場になります。
養子縁組のメリット
-
相続権が発生する
-
実子と同じ第一順位の法定相続人となり、法定相続分も実子と完全に同等です。
-
税法上の優遇措置がある
-
法定相続人の数が増えることで、「相続税の基礎控除額」や「生命保険金の非課税枠」が拡大し、結果的に相続税の負担を軽減できる可能性があります。
-
家族としての一体感が強まる
-
法律上も正式な親子となることで、家族の絆がより深まるという精神的なメリットもあります。
養子縁組の注意点・デメリット
メリットの大きい養子縁組ですが、実行する前によく理解しておくべき注意点もあります。
-
簡単には解消できない
-
養子縁組は、役所に届け出るだけで成立しますが、その関係を解消する「離縁」は簡単ではありません。
-
当事者間の合意がなければ、家庭裁判所での手続きが必要になります。
-
実子の相続分が減る
-
法定相続人が一人増えるため、あなたの実子がいる場合、その子の相続分は養子縁組前より少なくなります。
-
後々のトラブルを避けるためにも、実子には事前に事情を話し、理解を得ておくことが極めて重要です。
-
扶養義務が発生する
-
法律上の親子になるため、お互いに扶養の義務を負うことになります。
方法2:【養子縁組をしない】で財産を遺す
「実子との関係を考慮して、養子縁組まではしたくない…」
「養子縁組はせずに、感謝の気持ちとして財産の一部を遺したい」
様々な事情で養子縁組を選択しない場合でも、連れ子に財産を遺す方法はあります。
① 遺言書で財産を「遺贈」する
養子縁組をしない場合、最も有効なのが「遺言書」の作成です。
法定相続人以外の人に財産を遺すことを「遺贈(いぞう)」といい、遺言書に「A銀行の預金500万円を、妻の長男である〇〇(連れ子の名前)に遺贈する」と明確に記すことで、財産を渡すことができます。
【注意点】
-
・遺留分への配慮
-
他の相続人(実子など)には、最低限の取り分を主張できる「遺留分」という権利があります。
-
遺留分を侵害する内容の遺言書は、後日、親族間の深刻なトラブルに発展する可能性があります。
-
・相続税の2割加算
-
配偶者と一親等の血族(実子や親)以外が遺贈で財産を取得した場合、相続税額が2割加算されるルールがあります。
② 生命保険の受取人に指定する
ご自身が契約者・被保険者となる生命保険の「死亡保険金受取人」に連れ子を指定する方法です。
死亡保険金は、原則として受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割協議の対象外となります。
他の相続人の同意を得ることなく、連れ子に現金を直接遺せるのが大きなメリットです。
③ 生前贈与で渡しておく
あなたが生きているうちに、財産を連れ子に贈与する方法です。
年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからない「暦年贈与」の仕組みを活用できます。
ただし、亡くなる前7年以内(※)の贈与は相続財産に持ち戻される可能性があるなど、税法上のルールが複雑なため、実行する際は専門家への相談をおすすめします。
※2024年1月1日以降の贈与に関する制度改正
【司法書士が警鐘】実際にあった相続トラブル事例
対策を何もしなかったことで、円満だったはずの家族関係に亀裂が入ってしまうケースは後を絶ちません。
事例:『感謝してる』の言葉だけを信じた悲劇
Aさん(夫)は、妻の連れ子であるBさんと長年同居。
Aさんが高齢になってからは、Bさんが身の回りの世話や介護を献身的に行っていました。
Aさんは常々「Bには本当に感謝している。この家はBにやるからな」と口にしていましたが、養子縁組や遺言書の作成はしていませんでした。
Aさんの死後、遠方に住んでいたAさんの実子たちが相続人として現れ、「法律上、Bさんに相続権はない」と主張。
遺産分割協議の結果、Bさんは介護の貢献を全く評価されず、住み慣れた家を追い出されることになってしまいました。
口約束は何の効力も持ちません。
「言った」「言わない」の水掛け論は、家族の間に埋めがたい溝を作ってしまいます。
まとめ:円満な家族の未来のために、司法書士へご相談ください
再婚家庭の相続は、法律の知識だけでなく、それぞれの家族の感情にも深く関わるデリケートな問題です。
「うちの場合はどうなんだろう?」
「何から手をつければいいか分からない」
「家族にどう切り出せばいいか悩んでいる」
そんな時は、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所では、相続手続きと不動産登記の専門家として、あなたとご家族にとって最適な解決策をご提案します。
-
・誰が相続人になるのか、戸籍を収集して正確に確定します。
-
・あなたの想いを法的に有効な「遺言書」として形にするサポートをします。
-
・養子縁組や生前贈与の手続き、不動産の名義変更までワンストップで対応します。
大切な家族が、あなたの死後も笑顔でいられるように。
元気なうちに「想いを形にする」準備を始めることが、未来の家族への何よりの贈り物になります。
まずはお気軽にお話をお聞かせください。
まずはお気軽にご相談ください
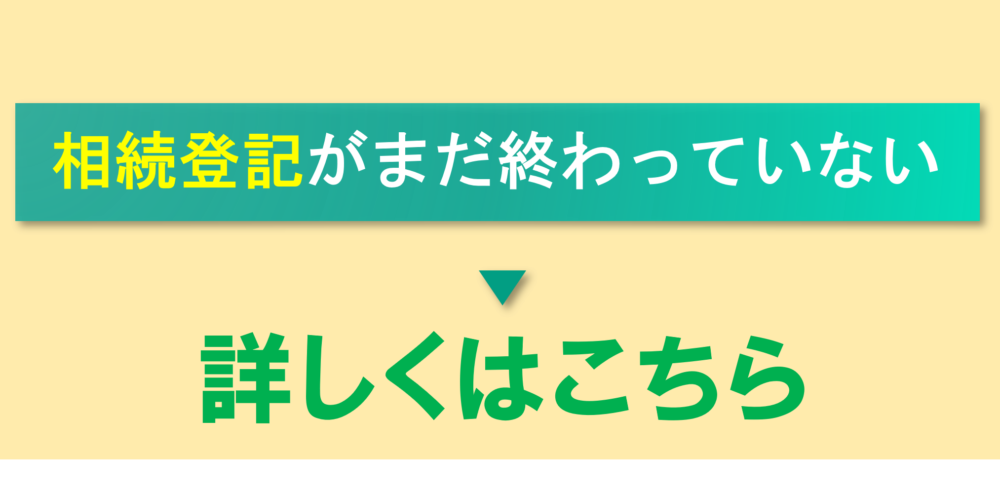 |
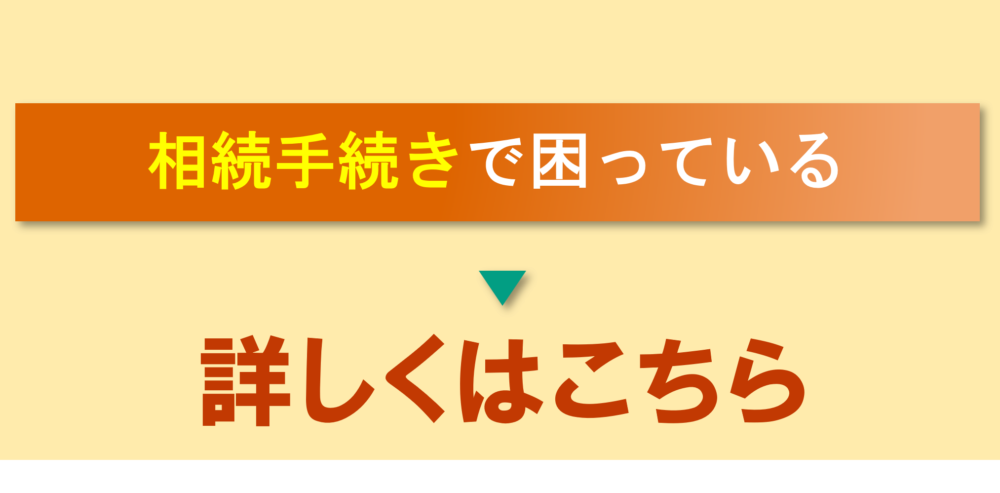 |
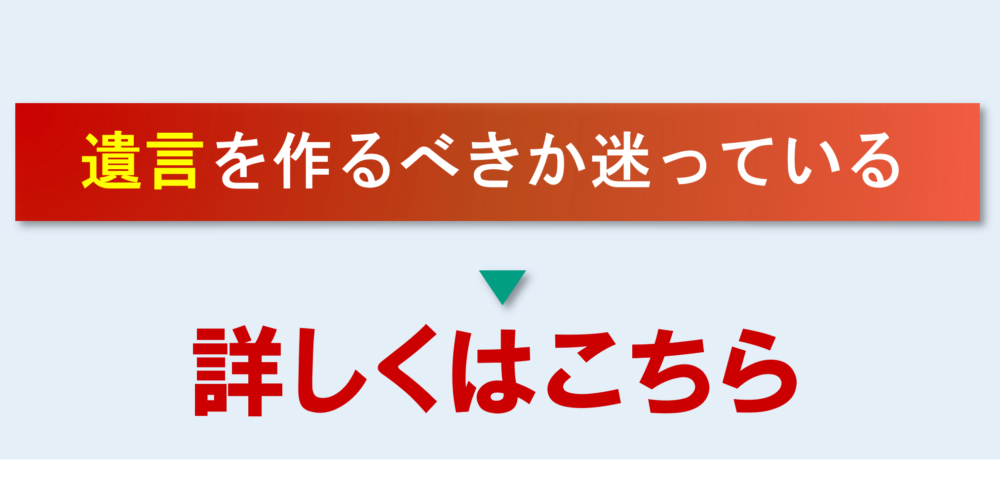 |
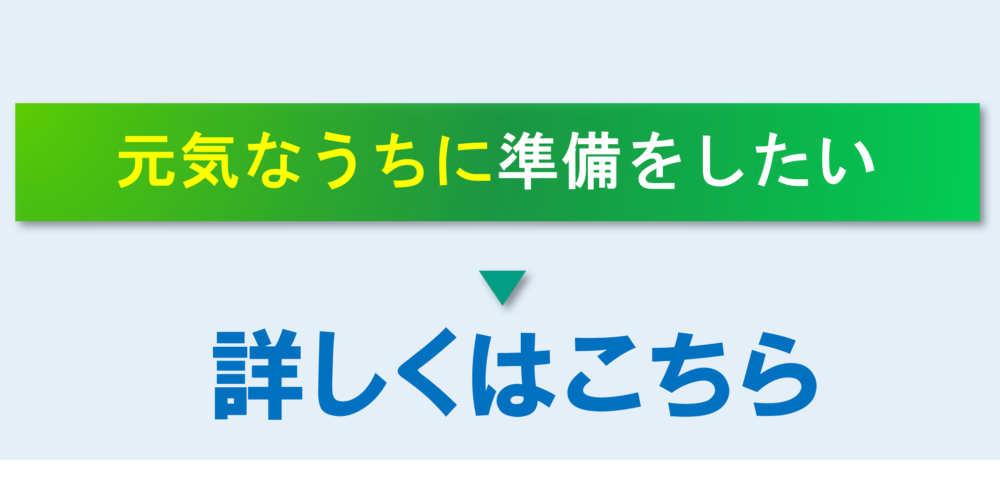 |
この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。
- 建物更生共済と相続
- 【相続手続きの全手順】いつまでに何をすべき?司法書士が流れを徹底解説
- 相続手続ライトプラン
- 【司法書士が解説!】再婚相手の連れ子に相続権は?養子縁組の有無とトラブル防止策
- 【司法書士の遺産整理業務】相続手続きを丸ごとお任せ|ご相談から完了までの流れ
- 複雑な相続手続き
- 相続人が多くて話がまとまらない場合
- 面識のない相続人(知らない相続人)がいる場合の相続手続き
- 相続人が海外在住の場合の手続きは?必要書類と相続手続きの流れを司法書士が解説!
- 相続人に未成年者がいる場合の相続手続きはどうする?
- 相続と行方不明者:知っておくべき手続きと注意点
- 相続人に認知症の方がいる場合のポイントを司法書士が解説!